駅前を歩きながら日課のように受け取るティッシュの他に、珍しく紙切れを受け取ってしまった彼は、それを愛しい彼女に渡し、往復ビンタを食らってしまった。
何がいけなかったのだ。
鼻にありたけのこよりティッシュを詰め込み、憔悴しきった顔でさらに悩みながら清四郎はいつもの道を歩いていた。
「ちょっとちょっとちょっと、お兄さん!」
いきなり肩を叩かれ振り向くと、30代半ばと思われる女性が数人、黄色いプラカードと籠を持って立っていた。
「君、それだけカッコイイんだから彼女いるでしょう。今時の若者には、とっても性病が流行っているのよ。避妊の目的だけじゃなく、ちゃんとコレ使いなさい」
「はぁ。」
おばさ・・・いや、お姉さん達は、「この子には絶対10個は必要よぉ〜きゃははは」(←その後の、絶倫に違いないという囁きは聞こえなかったことにしよう)と言いながら、数個のブツを渡してくれた。
「余計なお世話ですよ」
いつもなら冷たく断るところだが、憔悴している清四郎にとって、この日は妙なおばさ・・・いやお姉さん達の訳のわからない優しさすら身にしみた。
「どうも」
精一杯の御礼を言って、ブツを渡された10個+籠の中からせこくももう2個自分で受け取りポケットにつっこむと、清四郎はトボトボと家路についた。
日ざしは暖かいが、風はまだまだ冷たい春の気候。
魅録じゃあるまいし、日頃ポケットに手を突っ込み歩くような男ではないが、菊正宗清四郎、春寒に耐えられず行儀悪くも制服のポケットに手を入れた。
カサカサと触れるブツの山。
男の性で気にならない訳はなく、もらった一つをそっと手の平に包み込み目の前に持ってきた。
“たっぷりゼリーなめらか挿入”
!!!
何を僕は勘違いしていたのだ!
悠理が欲しいのは、僕・・・・僕・・・いや、僕自身!!
ラブホのチケットで満足しなかった悠理も、たっぷりゼリーなめらかプリンなネーミングのコレなら満足するに違いない!(←何か勘違い)
a@a@と書かれたピンクのパッケージも可愛らしい。
翌日、綺麗にラッピングしたスキンを差し出した彼が、悠理からグーパンチを食らったのは言うまでもない。
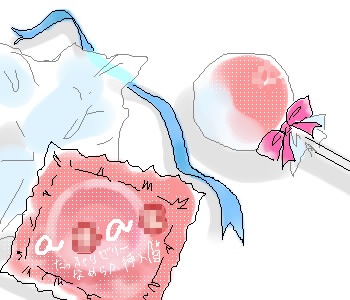
完!