|
清四郎がロンドンに行って、5年の月日が経った。
あたいに一言もなく。待っていてくれとも、一緒に来てくれとも言ってくれないままに。
だから、絶対待ってなんかやらないって思った。清四郎がロンドンで他の女とつきあおうと、あたいにはもう関係ない。あたいも、新しい男を見つけてやる!
──何度もそう思った。清四郎を見返してやるんだと。捨てられた女、ではなく、捨てた女になってやろうと。結婚には興味はないけど、それでもこれから先の人生、一人きりで生きていくんじゃあまりにも淋しすぎるじゃないか。
そう、清四郎より、もっともっといい男を見つけてやる。日本に帰ってきたあいつが、ぐうの音も出ないほどの、イイ男を。そのイイ男を腕にぶらさげて、日本に帰ってきたあいつを満面の笑顔で出迎えてやるんだ。
だけどそれは叶わない夢。……あいつよりイイ男なんて、一体どこにいる?
ふと気づけば、あたいは一人きり。
野梨子は親の勧めで見合いした音楽家とやらと結婚話が進んでいるし、去年、可憐と魅録は結婚してしまった。美童は相変わらず女には不自由はしてないようだし、清四郎以上に世界中を飛び回っている。
あたいだけだった。フラフラのんびりと生きて、地に足をつけない人生。どこかに就職するわけでもなく、週に一度はある様々なパーティに、剣菱家の一人として出席するだけの日々。パートナーを連れていくわけでもなく、学生時代と変わらず父ちゃんたちのお供で、それでも剣菱を目当てにあたいの回りに群がってくる男たちには目もくれず、パーティのご馳走をお腹いっぱい食べるだけで帰る。
何も変わらない。昔と同じ。
分かっていた。今のままじゃいけないってことくらい。
だけど仕方がなかった。どうすることもできない。
どんな男に会っても、清四郎の顔が脳裏に思い浮かんでしまう。顔も、頭も、力も、誰も清四郎には叶わない。父ちゃん母ちゃんが家に連れてくる意気込みだけは十分の男や、パーティで耳が腐っちゃうようなお世辞を並べ立てる、魂胆見え見えの男達の顔を一目見ただけで、直感的に分かってしまう。
その瞬間、ああ駄目だ──って。これも違う。あれも違う。あたいが欲しいのはこれじゃない。あたいの隣にいるべき男はこいつじゃない。
清四郎の幻を振り切らないかぎり、あたいは先に進めないんだ、きっと。
その繰り返し。5年間ずっと。清四郎が一度も日本に戻ってこなかった間何回も。
|
|
そうして気づけば、あたいは二十代も終わり──28歳になっていた。 |
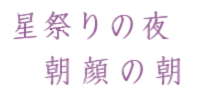
-1-
|
|
その清四郎が日本に戻ってくる。たった三日間の休み。先月届いたメールによると、ロンドンで進めていたプロジェクトが上手く行って、ようやく休みを取れたらしい。
しかし、あまりにも短い滞在時間だった。お昼すぎに成田に着いて、三日後の午前中にまたロンドンに向けて発ってしまう。
日本に戻ってきてもゆっくりできるわけでもなく、なんでも、仕事の関係でこちらで会わなくてはいけない人物が大勢いるらしい。
「すみませんね。どうしても外せない用があって」
そう、ロンドンに発つ前のメールには詫びの言葉が書いてあった。
すでに、剣菱グループの重鎮となっている清四郎にとって、昔の仲間と会える自由な時間は一日──いや一晩だけなのだ。
──7月7日、七夕の夜。
野梨子の家で、5年ぶりに有閑倶楽部の仲間が全員集まっての七夕祭り。野梨子の提案で、六人全員が浴衣に着替えている。
梅雨の晴れ間に、夜空には雄麗な天の川──といきたいところだったが、残念ながらここは東京の空。頼りなげな星がちらちらと瞬いているだけ。それでも濃紺に染まる天空は確かに晴れていて、織姫と彦星の、つかの間の逢瀬を叶えていた。
「5年ぶりだなんて、まるで織姫と彦星みたいよね」
可憐が料理を並べながら言った。縁側に並べた料理は、ロンドン生活が長かった清四郎のために和食が多い。素麺にうなちらし、茄子の揚げ浸し、サーモンと黒オリーブのマリネ、エビとほたての梅肉サラダなどなど。
そう言った可憐の視線の先には、すでに料理を皿いっぱいに盛った悠理がいたが、気づいているのかいないのか、ぺたんと縁側に座って、にんまりとした笑顔で料理を口に運んでいるだけだった。
「あら、清四郎はそんなロマンチストじゃありませんわよ」
代わりに野梨子が答えた。庭に飾った笹に、短冊飾りをつけている。背中ごしに向ける鋭い目は棘を含んでいた。その先には清四郎の姿がある。学生時代と変わらぬ秀麗な顔を笹飾りに向けて縁側に腰掛け、冷酒を口に運んでいる幼なじみに、容赦ない視線が矢のように突き刺さる。
「この日しか空いてませんでしたのでね」
清四郎は涼やかな顔で躱した。その背を、縁側に胡座をかいて座った魅録が、笑い含みにどやしつける。
「忙しい中、わざわざ時間を割いてやったんだって顔をしてるぜ」
「いえいえ、学生時代とまったく変わらないお前達に、5年ぶりに会えてよかったと思ってますよ」
「そう思うなら、もうちょっと長く休みをとればよかったじゃないか」
清四郎の隣で白ワイン片手にマリネをつまんでいた美童が言った。
「おや、美童に言われたくありませんね。お前だって、昔の仲間と会うよりも、あまたの女性と会う時間の方が長いじゃありませんか」
清四郎に切り替えされ、美童は浴衣の裾から余っている長い足をばたばたさせながらむすりと言い返した。
「仕方ないじゃないか。僕に会いたいって子ばっかりなんだからさ」
母国スウェーデンと日本、それからアメリカやフランスを行き来している美童は、皆に会うために半月の休みを取ってきている。半月と言っても、彼の場合は他にも会う約束をした日本女性が何人もいるのだから、昔の仲間と会える機会は数えるほどしかない。
「今日しか空いてなかったのでしたら、無理して私たちと会わなくてもよろしかったのよ、清四郎」
また野梨子が睨む。5年間の不義理を、少々のことでは許す気はなかった。その冷ややかな言葉に、他の3人も乗った。
「そうだよなあ。わざわざ俺たち5人全員に、同じメールをしなくてもな」
「そうよ。本当に教えたい人にだけ、日本に帰ることを教えればよかったのにねえ」
「せっかくの七夕なんだからさ、ロマンチックな夜を過ごしたかったのになあ。昔と変わらないメンバーじゃあねえ」
さすがの清四郎も矢継ぎ早に言われては、顔をしかめるしかないようだった。
「これは、友達と思えない言葉ですな。僕なんかに会いたくなかった、と言われている気がしますよ」
「あら、さすがの清四郎でも気づいてくれたようですわね。私、ロンドン生活の長さに、日本語を忘れてしまったのじゃないかしらと心配していましたのよ」
野梨子は皮肉を返しながら、眇で、話題に加わらず一心に可憐の料理をおいしそうに食べている悠理を見やった。
学生時代とかわらず見慣れた──なにより食欲が一番の悠理らしい姿だったが、皆は気づいていた。野梨子の家に全員が──いや、清四郎がやって来てから、悠理はとたんに落ち着きがなくなった。
「久しぶりですね」との清四郎の挨拶に、皆と同じく「元気だったんだな」と明るく答えたきり無口になった。可憐が縁側に料理を並べてからは、いつもと同じように食べ物に夢中という態度を見せたが、昔のような無邪気さは姿を消し、時折窺うように清四郎の横顔に目を向ける。視線を合わすのが怖いとでもいうように。
その清四郎は、5年前とまったく変わらない端正な面を皆に見せている。なんのこだわりもなく。聖プレジデントでの生徒会室で毎日見せていたように、幼なじみの野梨子にも、魅録にも──そして悠理にも。
ロンドンに行ってから5年。あまりの仕事の忙しさに、人の気持ちに昔以上に鈍感になったのではないかしら。
そのすました横顔を張り飛ばしたい気持ちを抑えて、野梨子は独りごちた。
|
| |
|
悠理と清四郎が、大学時代つきあっていたことは他の仲間も知っていた。大学を卒業した清四郎が剣菱グループに就職したとき、これはきっと遠からぬ未来、悠理と結婚するつもりだと誰もが思った。
時を経ず、清四郎が仕事でロンドンに転勤になったとき、悠理を連れて行くのだと信じて疑わなかった。
だが、悠理はロンドンに行かなかった。
どのくらいで日本に戻ってこられるのか分からないというのに、清四郎は悠理に何も言わないまま日本を去った。待っていてくれとも──ついてきてくれとも言わずに。
それでもきっと清四郎は悠理を愛しているに違いない。そう信じていて、気づけば、驚くべき早さで流れていってしまった5年の歳月。呆れたことに5年間、清四郎は一度も日本に帰ってこず、悠理といえば、清四郎という名を口にする回数はどんどん減ってきて、日本に残った美童以外の4人の間で、清四郎の話題をのぼらせることも少なくなった。
悠理がいないとき、野梨子は魅録に尋ねた。清四郎は、一体全体悠理をどう思ってるのかしら、と。
魅録は首を振った。なんとも思っていないという答えではなく、わからないという意味で。昔からそうだった。清四郎は、自分のことをあまり話さない。それでも、小さいときから兄妹のように育った野梨子なら、清四郎が考えていることは大体分かっていたが、こと悠理に関しては──どうしても分からなかった。
だけどきっと、悠理は今も清四郎のことを思っている。私たちに話さないのは、おそらく自分で自分の気持ちが分かってないから。胸の中に渦巻いている行き場のない思いを、言葉にするすべを持たないから。
可憐と魅録の結婚式の前々夜、女だけで悠理の部屋に泊まった折、悠理は言った。ぽつりと、心の奥底に長い間積もらせていた思いを漏らすように。
清四郎はきっと、ロンドンで外人の女とつきあってるんだよ、と。
そんなことないと、口を揃えて否定した野梨子と可憐に悠理は力なく首を振って、ベッドの上に体育座りをした膝にことんと額を落とした。
だって、もう4年も経ってる。こっちに戻ってこないのは、日本よりロンドンでの生活が楽しくなったからだよ。
きっと、何度も何度も自分に言い聞かせた言葉だったのだろう。いつも明るい悠理らしくない、疲れ果てたような掠れた声で呟いて。
悠理は苦しんでいた。4年間、清四郎の気持ちが掴めなくて。
あの清四郎が仕事に我を忘れることはあっても、女に夢中になって仲間のことを忘れることは絶対無いと、野梨子も可憐も分かっていた。
友達なら、長い間会えなくても相手の心を信じられる。月に一、二度届くメールの文字の中に、昔と変わらぬ友情が確かに存在していると感じ取ることができる。
でも──それが男女の仲となるとそうはいかない。会えなければ、相手の思いが定かではなくなる。そうして、自分の、相手に対する思いまでも不確かになってしまう。日々の報告めいたメールは、些細な言葉から簡単に疑惑を生じてしまうし、返事が少しでも遅れれば「嫌われたのではないか」と不安になる。
ましてや、悠理と清四郎の間に確かな約束は一つもない。
そしてまた、二人は恋愛というものに不慣れなのだから。
涙をこぼすわけでもなく、何もかも諦めきったかのようにため息を何度もつく悠理の姿には、野梨子も可憐ももう力づける言葉はかけてあげられなかった。だから、ただ悠理の肩を抱いた。小さく丸めた背中を何度も撫でた。悠理の清四郎を思う気持ちが、ロンドンと東京の距離を超えて、彼の元に届くようにと祈りながら。
|
| |
|
それから1年後、ようやく悠理の願いは叶えられ、清四郎が日本に帰ってきた。二人きりで会える時間を作ってあげたいと思っていながらも、清四郎の都合がつかず、せっかく予定空いた今日という日も、悠理は皆と一緒でなければ会わないと強情を張った。だからこうやって場をセッティングしたというのに、二人の間はロンドンと東京の如く、今も遠く隔たっている。
一年に一度、織姫と彦星が会うことのできる七夕という日。5年という時も超えて、二人がつきあっていた頃のように──とまではいかないまでも、高校生の頃のような喧嘩をしながらも心の底では通じ合っている二人を見たかったのに、どうやらまだ、清四郎と悠理の間には大きな天の川が横たわっているようだった。
ここは、悠理が訊けないことを私が訊かなくては。
野梨子は毅然と頭を上げた。そして、縁側に腰掛けている清四郎の前に立ちはだかる。
「清四郎、私、訊きたいことがありますのよ」
「ほう、一体なんでしょう。野梨子らしくない、怖い顔をして」
あきらかにけんか腰の野梨子に、清四郎はしれっとした顔で答える。悠理は、びくりと身を震わせて料理を運ぶ手を止め、野梨子をおそるおそる見上げていた。そして、野梨子の意を承知している可憐たちは、息を飲んだように清四郎を見つめた。
「どうして、今まで日本に戻ってきませんでしたの?」
「言ったでしょう。仕事が忙しかったんですよ」
「あなたが仕事に生き甲斐を感じているのは、重々承知していますわ。でも、5年間、一度も日本に戻るために休みをとれませんでしたの?」
「そうですよ。ありがたいことに、僕がいないと先に進めないプロジェクトに関わっていましたのでね」
それは、何度もメールや電話で聞いた言葉だった。野梨子が知りたかったのは清四郎の本音。そんな風に顔色一つ変えずに言ってのける言葉ではない。
「それは、言い訳にしか聞こえないぜ」
次の言葉を探っているうちに、魅録が口を挟んだ。清四郎は鼻白んだように魅録に不機嫌な視線を向ける。
「失敬な。僕が嘘を言っているとでも?」
「私たちがいいたいのはそんな事ではありませんわ。あなたは、私たちと会う時間を積極的に作ろうとしなかった──違いますかしら?」
「そうだよ、本当に会いたいって思ったら、時間なんて結構作れるもんだよ」
数多の女性とつきあう時間をどうやってか捻出している美童が言うと、意外に説得力がある。
「そうですわ。ロンドンから東京まで12時間。四日もあれば、十分に行って帰れますでしょう? 休みが無理なら、今回みたいに日本での仕事を作って戻ってくればいいんですわ」
「無茶をいいますな。そんな簡単にロンドンと日本を往復できるわけがないでしょう」
清四郎は苦笑した。野梨子や他の仲間の反論の言葉を、真面目に受け取っているふうには見えなかった。可憐が身を乗り出して、言葉を継いだ。
「でも……でも、清四郎、あたしたちはあんたに会いたかったのよ。メールや電話だけじゃあ、あんたが元気にしてるなんて分からないじゃない。心配していたのよ、みんな──それに、悠理も」
悠理一人が清四郎に背を向けて、一心不乱に食べている。まるで意地になっているかのように、次から次へと口の中に。可憐と野梨子で用意した心づくしの料理は、悠理以外の誰もほとんど手をつけないまま、悠理の底なしの胃の中へ消えてしまっていた。
「ねえ、悠理。あんたも清四郎のこと心配していたわよね?」
可憐は悲鳴に近い声で言った。悠理の肩がぴくりと震える。手を止め、恐る恐る──というように振り返り、一瞬躊躇った後にかっと笑った。
「あたいは、清四郎のこと信じてるからさ、心配はしてなかったじょ」
「悠理! そんな、強がり言わなくても」
「だって、清四郎が仕事で頑張ってるってこと、父ちゃんから何度も聞いてたしさ、清四郎のことだから、絶対仕事が成功するまで戻ってこないって分かってたし」
「悠理……」
一番に清四郎の不義理を責めるべき悠理一人が、清四郎を庇っていた。この場に漂う険悪なムードを振り払おうと、無理にでも明るく笑って。そして黙り込んでしまった仲間たちの顔を眺めわたし、最後に清四郎に向けて「ほらっ」と料理の皿を差し出した。その皿の上には、うなちらしが山のように盛られていた。
「それにさ、せっかく5年ぶりに会えたんだからさ、楽しくしようよ。ほら、可憐の料理、すんごいおいしいじょ。清四郎もさ、ロンドンのまずい料理5年も食べてたんだから、日本食に飢えてんだろ? 早く食べないとさあ、あたいが全部食べてしまうかんな。いいのかよ?」
野梨子はもう清四郎を責めることはできなかった。そして、悠理の笑顔があまりにも痛々しくて、これ以上目にすることはできなかった。
「そうですわね、七夕の夜なんですもの。喧嘩なんてあまりにも無粋でしたわね」
清四郎は黙ってその皿を受け取った。悠理と、今夜初めて視線が合う。確かに、清四郎の目の中には後悔のようなものが見えた──少なくとも、野梨子にはそう見えた。
これ以上の言葉は必要ない。足りない言葉は疑惑を生み出すけれど、多すぎる言葉は相手を追い詰めてしまう。
きっと、清四郎の胸の中に悠理の思いは届いているだろう。
野梨子はふうと息を吐いて天を見上げた。南天にある月は雲居にかかり、おぼろな光が七夕飾りが風に揺れる笹を照らしていた。すでに、織姫と彦星は天の川を超えて逢瀬の時を迎えているだろうか。そこにはきっと、どんな言葉も意味を持たないに違いない。
そしてきっと、悠理と清四郎はどんなに遠くに離れていても、織姫と彦星のように心は結ばれているのだわ。
そう私が信じなくては、あまりにも悲しすぎますもの。
「……清四郎」
野梨子はようやく肩から力を抜いて、その名を呼んだ。清四郎はちらしずしを口に運んでいるところだった。その後ろで、悠理が清四郎以上の大口を開けて、ちらしずしを食べている。その顔には先程までのつくりものめいた笑みではなく、学生時代と同じ無邪気な笑みがあった。
清四郎が俯いていた顔を上げる。見慣れた、小憎らしいほど自信満々の顔。野梨子は清四郎の隣に腰掛け、脇に置いてあった酒を差し出した。透明なガラスに入った酒はキンと冷えて、涼しげな水滴がみっしりと浮いている。
「──悠理に免じて、今回は許してあげますわ」
清四郎は何も言わなかった。ただ黙って野梨子の酌を受け、旨そうに透明な酒を飲み干した。
|