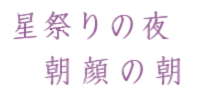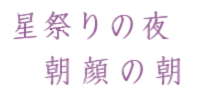|
魂が抜かれてしまった人形のようになって、悠理はふらふらと部屋に戻り朝食を食べた。いつものような食欲を見せなかったお嬢様に、メイドたちが心配そうに声をかけたが、悠理にはその声も聞こえていなかった。
部屋に置いた朝顔の鉢を見つめているうちに、少しずつ現実が見えてきた。
僕の気持ちだと、清四郎は言った。この朝顔に一体どんな意味が込められているんだろう。
やっぱり分からない。あたい一人じゃどうすることもできない。野梨子と可憐に助けてもらわなきゃ。
そう思うといてもたってもいられなくなった。
悠理は鉢植えを抱えて、急いで野梨子の家に向かった。その隣、菊正宗家はしんと静まっている。きっと清四郎は家を出て、もう成田に向かっているに違いない。
先に連絡していたから、野梨子はいたわるような儚げな笑顔を向けて、悠理を出迎えてくれた。
通されたのは昨夜と同じ座敷。縁側に朝顔の鉢植えを置いて、野梨子も黙ったまま可憐を待った。そして、可憐はやってくるなり額に浮いた汗も拭かず、悠理の目の前にある朝顔をまじまじと見つめ、首をかしげながら尋ねた。
「これを、清四郎が? 僕の気持ちって言ったの?」
「う、うん。確かにそう言った」
可憐のきれいに整えられた眉がひそめられる。
「普通、男が女にあげるって言ったらもっときれいな花束よねえ。朝顔なんて……それも鉢植えよぉ? どういうつもりなのかしら。野梨子、あんたならイミ分かる?」
「そうですわね……」
野梨子が呟いて、萎れ始めた朝顔の花に手を触れた。大きく開いた花は力なく俯いて、鮮やかな色も失いつつあった。
「確かに清四郎らしくありませんわ。ロンドンに発つ日に渡すような花じゃありませんものね」
「二人にも、やっぱり分からないのかあ」
悠理は盛大なため息をついた。僕の気持ち、と清四郎は言ったが、女に花を渡すというありきたりの意味がたったひとつあるだけで、その裏に隠されたものなどなにもないのかもしれない。
「あ、もしかしたら花言葉! 花言葉かもしれないわよ?」
可憐がぱちりと指を鳴らした。
「可憐! きっとそれだじょ〜!」
悠理は目の前がぱあっと明るくなった気がした。しかし、野梨子一人眉を曇らせている。
「花言葉はいい案だと思いますけれど、清四郎がそんなものに興味あると思いませんわ。第一、今朝朝顔市で買ってきたものなのでしょう? 花言葉を調べる時間なんてあったのかしら」
「それはそうかもしれないけど……でも、一応、花言葉調べてみたら?」
可憐の提案に、野梨子は渋々うなずいて座敷を出てゆき、掌に載るくらいの花言葉の本を持ってきた。可憐と悠理が本を覗き込む。
朝顔の花言葉──はかない恋・愛情の絆・固い約束。
「ううん……当たってるような、当たってないような」
可憐は頭を抱えた。野梨子もじっと、朝顔のカラー写真が載ったページに視線を落としながら呟く。
「はかない恋というのは違いますわよね。愛情の絆、というのは合っているような気もしますけれど……悠理、清四郎となにか約束を交わしませんでした?」
「ううーん……約束っていったって、この朝顔の世話はあたいがするって言ったくらいでー」
さすがに色恋に鈍い悠理にも、それは全くの見当違いと分かっている。
「その他には? たとえば、5年前。ロンドンに清四郎が行く前、何か約束しなかった?」
「ええー?」
悠理は頭を抱え込んだ。5年前……悠理の心許ない頭でも、清四郎がロンドンに発った日、そして、ロンドンに行くと悠理に言った夜の出来事は覚えている。どんなにショックで悲しかったか。だけれども、約束なんかなにも交わさなかった。第一、どんなものであっても清四郎と約束していたのなら、今のどっちつかずの苦しみなんか、きっと悠理には無縁のものだったに違いない。
「なかったと思うじょ。あたいが……気づいてないだけなのかもしんないけど」
その頼りない呟きに、可憐が盛大なため息をついた。ふう、と肩を落として、悠理を見つめる。その視線には仲間を気遣う優しさがあふれていた。
「あんたのことをよく分かってる清四郎が、そんな気づかないような約束をするわけないわよねえ。じゃあ、朝顔には深い意味はないのかしら」
「そうですわねえ」
野梨子は朝顔に手を伸ばした。花は蒸し暑い梅雨空の下しおれきってしまい、青々とした葉の中に埋もれそうになっている。
「……あら?」
朝顔の蔓を触っていた野梨子が、何かに気づいて怪訝そうに首をかしげる。両手を伸ばして何かを探り──その掌には折りたたまれた紙があった。
「なにこれ?」
「蔓の下のほうに結んでありましたの」
悠理が身を乗り出す。野梨子は紙を広げた。
すかし入りの薄紫色の和紙で、野梨子の掌が透けて見えるほど薄い。そして、その上には流れるような達筆で短い文章が書かれていた。
「なになに? 何が書いてあんの?」
悠理には文字の判読ができなかった。清四郎の文字は見慣れているが、筆で書いた草書は目にしたことがない。
「あたしにも読めないわ。野梨子、あんたなら分かるんでしょ?」
「ええ……そうですわね……あら、もしかしたら、これ……」
野梨子は何度も視線を和紙の上に走らせた。和紙に書かれた文字を、野梨子の華奢な一差し指がなぞってゆく。何かを必死に思い出すように伏せられた睫毛が揺れ、声に出さずに口の中で呟いている。
「清四郎の手紙かなんか?」
悠理は声をひそめて尋ねた。野梨子がはっと面をあげた。
可憐と悠理はもう和紙を見ていなかった。野梨子だけをひたすらに見つめている──たった一つのよすがとでも言うように。
「ええ、清四郎が悠理にあてた手紙……のようなものだと思いますわ」
しっかりとうなずいて、わずか2行の手紙を悠理の掌に載せる。悠理の眉が不思議そうに曇る。
「なんて書いてあったの?」
野梨子はそれに答えず、立ち上がって再び座敷を出ていった。そうして一冊の本を手に戻ってきた。
「本? それがどうしたの?」
「清四郎は、これを元にしたのですわ」
|